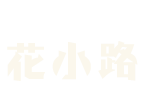地に落ちた蝉は腹を見せたまま幾度か足掻き、力尽きて動かなくなった。雄一は指の腹で花壇の黒土を掘り、蝉の亡骸を横たえた。
母もそうだった、と、雄一は思う。棺の中の母は、昆虫の標本のように痩せさらばえて、かさかさに乾いていた。蝉の腹が、柔らかな黒土に覆われていく。人間とて、やがては土に還るのだ。母も、雄一も、きっと。
背を丸め杖に縋って歩いていた母に悪性腫瘍が見つかったとき、雄一は迷わず早期退職の道を選んだ。二年半だった。退職金のおかげで金銭面に問題はなかったが、精神的には厳しい日々が続いた。長い闘病生活の間に、彼女の食事は、柔らかめのご飯から流動食に変わった。流動食さえ拒むようになってからは、早かったと思う。
ゆうすけ、と、記憶の中の母が呼ぶ。長男の名前は雄一なのに、なぜか母は雄一のことをゆうすけと呼びならわした。ゆうすけ、ほれ、しゃきっとすろ。
煉瓦造り風の公衆トイレで指先を丹念に洗い、外に引き返す。娘も息子も家を出て、父親はとうの昔に鬼籍に入っていた。連れ合いも四年前、交通事故で亡くしてしまった。雄一はとうとう一人になった。長男夫婦はしきりに同居を勧めてくれるが、義理の娘に気を遣わせるのも悪いので、雄一は一人暮らしを続けている。一人になって二か月近く経とうとしているのに、ふとした瞬間に孤独を覚えて、押しつぶされそうになる。山形の夏は蒸し暑く、雄一の食欲を削いでいる。今日だってそうだ、雄一はどうにか胃袋に食べ物を押し込んで生きている。生きているのかどうかさえ、よく分からないままだ。
旧県庁からは日陰ばかりを選んで歩いた。雄一が歩を進めるたび、熱風が吹きつけた。朝晩こそ涼しい風が吹くものの、昼下がりの山形には、まだ暑さが残っている。
黒い柵越しに、青い植木鉢が覗いていた。朝顔の花はすっかりしぼんで、傾きはじめた太陽を物憂げに見つめている。プラスティックの、四角い鉢の上部には、サインペンで名前が書かれていた。雄一は民家を見上げ、彼らの生活の営みを思った。自分とはもう、縁のない世界だ。
実家のそこかしこに、母の面影が残っている。逃げるように雄一は外に出て、日が沈めば実家へ戻る。けれどそこに、雄一の帰りを待つものはない。
雄一は不意に、家に帰りたくない気分になった。そういうときは酒場で時間を潰して家に戻る。酔いさえ回ってしまえば、空っぽの家もただの寝床だった。
馴染みの店の暖簾をくぐると、冷房の風と共に脂の匂いが流れ出てきた。胃弱の雄一はその匂いだけで酔ってしまいそうになり、慌てて唇を結んだ。引き返そうかと惑った一瞬の隙に、店主は雄一を認め、「こんばんは」と声を掛けた。
「雄一さん。お母さん、具合どう」
「今日が四十九日」
「あれ、亡くなったの?」
雄一は頷いた。
「ご愁傷さま」
すぐさま表情を引き締め、柔らかい声で店主は雄一をねぎらった。職業柄か、店主の記憶力はすこぶる良く、取るに足りないことまで事細かに覚えている。
「ありがとう。土日に法要が終わって、おかげさまでひと段落ついたところ。覚悟はできてたんだけど、いざ亡くなると、なんだか、ねえ」
言いながら、そうか母は亡くなったのだ、と、雄一は改めて失意に沈んだ。ただでさえ、肉親の死はこたえた。母を看取る日が来ることは分かっていたが、いざ母を亡くしてみると、自らの老いも思い起こさせられるようで、気が滅入った。ぐっと老け込んでしまった気にさえなっている。順当にいけば、血族の中で次に亡くなるのは雄一だろう。
「なにになさいますか?」
「そうだな、混んでるみたいだし、飲んでから考えさせてもらおうかな。生中ひとつ」
店主は神妙な面持ちで、「まず、ゆっくりしていって」と頷いた。ゆっくりするつもりはないが、健康診断が気になりはじめてからは、雄一の飲酒ペースは遅い。ビールをちびちびと飲んでいたところへ、入口の戸が開き、若い女性が店内に入ってきた。三十歳代だろうか。薄暗い店内で、深紅のネイルはやけに鮮やかだった。
「こんばんは。一人なんだけど、空いてる? ――よかった。ああ、喉渇いた。ビールちょうだい、生の、中ジョッキ」
短いやり取りののち、見知らぬ女は極めて自然に雄一の隣に陣取った。拒む気になれなかったのは、酔いが回りはじめているせいだろう。
アルバイトの若者は、すぐにビールを持ってきた。雄一はお通しをつまみながら彼女を盗み見た。彼女は喉を鳴らしてビールを飲んだ。深紅のルージュがやけになまめかしかった。
「強いんだね、お酒」
女がジョッキを置くのを待って、雄一は話しかけた。ジョッキの中のビールは目に見えて減っていた。
「そうかな? 暑かったでしょう。やっぱりね、こういう日はビールがおいしい」
深紅の唇が綺麗な弧を描いた。雄一より一回り以上若いだろうに、女は敬語のひとつも使おうとしない。腹を立てるよりむしろほほえましく思うのは、彼女の資質の成せる業だろう。
「お兄さん、焼き鳥盛り合わせ、ひとつ。塩ね」
お兄さんという年でもないだろうに、店主はまんざらでもなさそうな顔で、「盛り一丁」と若者に指示を出した。
「綺麗な腕だね。筋肉ついてる」
彼女は雄一の腕をつついた。
「ああ、自宅介護をしていたから」
感慨にふけりながら、雄一は頷いた。腕についた筋肉は、介護の思わぬ副産物だった。
図書館や本屋に通い、負担の少ない介助方法を学んではみたが、力の必要な場面も皆無ではなかった。
「自宅介護? 親御さん?」
「うん」
雄一は頷いた。
「そっか、お疲れさま。――私だったら、さっさと介護施設に入れちゃうな」
指先が、ねぎらうように雄一の腕を撫でた。ビールジョッキを握っていた、ほっそりとした指は、水滴に濡れて冷たかった。
「その方が幸せだったのかもしれないね」
六十年近く生きてきた雄一にとって、介護ははじめての経験だった。子どもを育てるのとは訳が違う。子どもは日々成長していくが、進行していく母の衰えを止める手段はなかった。全力を尽くしたとは思いたいが、希望通りの介護ができたのかどうかと問われると、何も言えなくなる。自宅で世話すると決めたのは、雄一のエゴだったのかもしれない。
感謝されなかったのは、育児と同じだ。それでも、小さな幸せを見つけることはできたと思う。遠くのスーパーで買ってきた介護用飲料を、母が好んで飲んでくれたこと。母と共に出かけた野草園の花が綺麗だったこと。最初の一年で、靴下をたくさん編んでくれたこと。――母は日に日に編み物を忘れていって、死ぬ間際に編んだものは、ただ
の毛糸の塊でしかなかったけれど。
彼女は黙り込んだまま、雄一のポロシャツの襟元に手を伸ばした。昼に食べた、コンビニエンスストアの焼きそばがこびりついていた。乾ききった茶色の切れ端を、真っ赤な爪が剥ぎ取って、灰皿に落とした。
「今日だって、紙おむつ、二十二枚入り、千三百円でさ。安いでしょう? って言っても分かんないか、結構安いんだ。丸つけようと思ってペンば探して、ああ、もう母ちゃんはいないんだった、って。紙おむつなんかいらなかったんだって」
問わず語りに零しながら、雄一は確信していた。聞いてくれる人が欲しかったのだ。解決策の見えない泣き言を。生産性の欠片もない愚痴を。雄一はビールを呷った。酔いのせいにして、すべて吐き出してしまいたかった。明日からまた、変化のない、重苦しい日々を過ごすのだ。それくらいの我儘は許されると思った。
「結局さ」
彼女は唇を尖らせ、自らの前髪を幾度か左手で梳いた。つやのある髪は力強く彼女の指に逆らい、元の流れに戻っていった。
「結局のところ、幸せだったかどうかなんて、本人にしか分からないんだよね。だから残された人は色々考えちゃう。でも、最善を尽くしたんだし、なんていうかな、親御さんって、子どもからもらうプレゼントなら、なんだって嬉しいっていうじゃない。私は、父ちゃんも母ちゃんも、事故っていうのかな、早くに亡くしちゃって。だから、親孝行らしい親孝行ってできなかったんだ。……あ、なんだかしみったれた話になっちゃった? ごめんね」
雄一の表情をちらりとうかがい、彼女は笑みを作って、焼き鳥の串に手を伸ばした。
「だけど、子どもを育てて、最近になって思うのは、大抵の親ってのはね、子どもが幸せに生きてるだけで嬉しいんだなあ、って」
「んだべが」
「んだよ」
彼女は頷き、砂肝に噛りついた。串が動くたび、焼き鳥の脂が、ぼたぼたと皿に落ちた。
「ところで、なにか食べないの? 飲んでばかりじゃ胃に悪いよ」
「ああ、――うん、そうだね」
雄一は急に空腹を覚えた。ブランチといえば聞こえはいいが、朝食抜きで食べた焼きそばは、とうに消化されたに違いなかった。彼女の皿を指差して、店主と視線を合わせた。
「彼女と同じものを、タレで」
彼女は短く、鼻にかかった笑い声をあげた。からかわれるだろうか、と雄一はカウンターの向こうの店主を見遣った。予想に反して、店主は短く是と答え、火の上に淡々と串を並べはじめた。
焼き鳥のタレは時折鶏の脂を吸って滴となり、熾の炭に落ちて、ぱちりと爆ぜる。た
れの香りを帯びた煙が鶏肉を燻す。だから炭火の焼き鳥はおいしいのだ。奥の席から、酔客の下卑た笑い声が聞こえてきた。
「ねえ、お孫さん、いる?」
彼女は不意に雄一に尋ねた。
「いるよ」
焼き鳥の脂がビールと共に胃に流れて、わずかに痛みが走ったが、雄一は平静を装った。後で胃腸薬を飲めばいい。焼き鳥のタレは甘く、冷たいビールによく合った。
孫とは、法要で顔を合わせたばかりだ。雄一は頷いた。写真を見せようと携帯電話を取り出し、雄一はボタンを操作した。十数年前には、通話できて写真が撮れて音楽も聴ける端末など、SFの中の話と思っていた。会社勤めをしていた分、同世代の中ではこの手の電子機器を使いこなしている方だと自負してはいるが、普段使わないアルバム機
能は、いざ使おうとすると手間取ってしまう。酔いも手伝ってか、操作が一向に思い出せない。
「夏休みでしょう? 誘っちゃいなよ、遊びにおいでって」
雄一がもたもたと携帯電話を操作している間に、彼女はけしかけるように言った。
「簡単に言うねえ」
二人の息子は家を出て、それぞれ別の家庭を築いた。一人になったからといって、今更、よその家の生活に関わるのは気が引けた。
孫を呼ぼうにも、部屋はずっと散らかったままだ。そもそも、男やもめの暮らしで孫をどうもてなしていいのか分からない。初七日を終えた頃から、実家を訪れるのは雄一の兄弟連中と、息子二人に限られていた。
「家がいやなら、リナワールドとか、いろいろあるでしょう」
「リナワールド?」
「山交ランドのこと」
「知ってる、知ってる」
一昔前に名前が変わった遊園地のことだ。昼のワイドショーの合間に時折コマーシャルが流れるが、実のところ、雄一はまだ一度も足を踏み入れたことがない。
操作中の携帯電話が急に震えて、雄一は慌てた。連絡先を確かめ、「ちょっと失礼」と断って電話に出た。息子だった。通話の相手の名前が表示されるのも、十数年前には考えられなかったことだ。
「もしもし」
『ああ、親父? なんとしったべど思って、電話したんだっけ』
オレオレ詐欺が横行してはいるものの、上の息子の声を、雄一が聞き間違うはずもなかった。雄一の母が亡くなってからこちら、兄弟はかわるがわる雄一に電話を寄越すようになった。疎ましいと思う一方、嬉しいとも思う。
「今焼き鳥食べ来て、飲んでだ」
『あ、んだっけのが。邪魔したっけ?』
「いや」
「息子さん? 息子さんなんでしょう? 遊びに来いって言いなよ」
彼女は声をひそめ、雄一の二の腕をつついた。分かった、と、雄一は彼女の指を払いのけた。
「今度、お前休みん時にでも、遊びさ来ねが、なっちゃんば連れで」
『再来週の土曜日だば行がれっけど、夏樹の予定ば聞がねど答えらんね』
「んだが。じいちゃんリナワールドさ行ってみっだいのよって、伝えてける?」
『夏樹、リナワールド行がねがどは、山形のじいちゃんが。……行ぐっつってだ』
「んだが」
かすかではあるが、電話越しに、孫の弾んだ声が聞こえてくる。
「やったあ」
彼女は快哉を叫んでジョッキを掲げ、残りのビールを一気に飲み干した。
『親父、その女の人、誰?』
訝しむように息子は尋ねた。雄一の妻は亡くなっている。やましいところなどないが、端から見れば不倫に近いのかもしれない。雄一は動揺した。
「違う違う、一緒に飲んでる人」
なにが違うというのだろう。余計に誤解を招いてしまった気がするが、後の祭りだ。
「また連絡すっから!」と、雄一は一方的に通話を切った。息子がなにか話していた気がするが、用があるなら掛けなおしてくるだろう。
「今日はありがとう。……奢るよ」
最後の一口を片付けて、雄一は彼女に宣言した。それだけの価値はあると思った。少なくとも再来週までは、小さな楽しみを糧にして、生きていけそうな気がした。
「本当? ごちそうさま」
彼女は弾んだ声で礼を告げ、外に出た。ジョッキから滴った水が、小さな水たまりを作っていた。
勘定を済ませて、夜風の吹く表へ出ると、彼女が両手を広げて歩み寄ってきた。雄一を置いて出たと思っていたが、待っていてくれたのらしい。
「ありがとう」
彼女は雄一を抱きすくめた。酔っているとはいえ、ひどく馴れ馴れしい。雄一はおっかなびっくり、彼女の背中を撫でた。
満足したのだろうか、やがて彼女は体を離し、はずかしそうにはにかんで手を振った。
「ありがとうね、ゆうすけ」
踵を返して、彼女は夜の花小路を歩いていく。凛とした背中に、なにより「ゆうすけ」という呼び方に、明らかな既視感を覚えて、雄一は目を瞠った。
「……かあさん」
呼びかけた途端、彼女の背は宵闇に飲まれるように消えてしまった。
黄色みを帯びた看板が、晩夏のぬるい闇をほのかに照らしている。雄一はもう一度「かあさん」と呟き、酒に火照る両手で顔を覆った