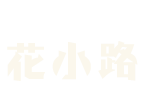明日から九月、という日、私のもとに一つの小包みが届いた。
差出人は草加恭子と記されている。住所は東京だ。
(誰だろう)見覚えない名前に首をかしげながら、包装を開けてみた。
「あっ」
それは一冊のノートであった。
(圭一さんのスケッチだ。でも、どうして)ハガキが添えてあった。
――突然のお便りをお許し下さい。私は草加恭子と申します。二条圭一の姉でございます。実は半年前に弟の圭一が交通事故にあい、亡くなりました。――
頭が混乱してくる。グルグルめぐっている。――、弟の部屋を整理しました。そのノートの中に、あなた様のお名前と住所があり、現在いらっしゃるか不安のまま、ぶしつけながら、送らせていただきました。弟がスケッチしたものです。そんな人がいたな、と思い出していただけたら幸いです。――
(圭一さんが死んだ……。)最後に逢ったのはいつだったろう。(もう五年になるくらいかもしれない)
彼と私は恋人ではなかった。
単なる顔なじみ。でも、好きだった。おそらく彼も。
私には遠距離恋愛の恋人がいた。長い交際期間を経て、来月結婚するのだ。このマンションも二週間後に引きはらい、私は東京に行く。
何というタイミングだろう。
圭一は五歳年上だった。当時三十三歳。職業は会社員。建設会社に勤務しており、東北エリアを担当していた。出身は札幌。趣味は絵を書くこと。小さなスケッチ本をいつも持ち歩いていた。
どこか品があり、頭も良さそうだった。そう、文学青年タイプだった。住まいは東京で山形には出張で度々来ていた。
圭一と出逢ったのは、十一月の寒い夜。
木々が揺れて寒くなり、風も冷たい。冬へ向かう嫌な季節。
あの頃私は忙しかった。
そして、よく飲んだ。
仕事を終えて会社を出たときの空気、夕方が夜になろうとする匂いが好きなのだった。
バス時刻の待ち合いの時間、バーに行ってビールを一、二杯飲む。それが私の楽しみのひとつだった。彼氏は離れていたし、基本一人だった。その時の気分なので、いちいち友人を誘うこともなかった。(まるでオヤジのよう)と思っていたことを思い出す。
そして(もう少し飲もう)の時、タクシーに乗るのだ。
「花小路まで」
それも日常だった。
花小路の入口をぬけて左へ入り、舗装された小路を進む。古くからのお店が連なっている。車をその先の奥まで案内する。
「すごい通な所で飲むのですね」と運転手さんによく言われた。十メートルほど脇道を歩くと店看板が出むかえる。
『u』
マンション隣で喫茶店を営むママが、夜はここでスナックを開いていた。
一人暮らしの私は、ママにとてもお世話になった。昼も夜も。今も昼のランチを食べてきたばかりで、
「あと二週間で友美ちゃんとお別れね」
そんな会話を交わしてきたところだった。
『u』のママは以前、他の場所で店をしていたらしい。いろいろあって、再び店を始めた。お子さんを一人で育てていて、とにかく偉い人なのである。
圭一は仕事関係の人に連れられて来ていた。
少しばかりテンションが上がった私が、
「ママ、今日もよろしく」
カウンターにすべり込む。何も言わなくともギンギンに冷えた生ビールがくる。グラスが冷凍庫に入っている為、とても冷たい。
客はなじみの人ばかりで、ママを通じて皆々が、知り合いになっていく感じであった。
たまに知らない客がいると、少し緊張した。あの日もそうだった。全く知らない客人が二人、カウンター席で談笑していた。
その一人が圭一だった。
ママと乾杯し、またすぐおかわりをする。
「何だか雪が降りそうなくらい、風がつめたいの。」
と言いながら、真夏のように飲んでいく。
「お酒強そうですね。」
圭一が、ママと私を見て話しかけてきた。
「強くはないけど、好き。」
「ビールだけ?」
「最近はこればっかりかなぁ。三、四年前はバーボンだったけれど。流行ったでしょ」
ママがボトルを出してきて、
「友美ちゃん、これあるからね。」
バーボンとジンを置いた。
「ああ、そうだよね。ママにわざわざ注文して入れてもらったのにね。でも今日は止めておく。また別の日に。センチな時にするわ。」
「彼とはうまくいってる?」
「まあ、ね。先週東京に行ってきた。仕事がとても忙しいって。」
彼はここに来たことがない。
「友美の場所は犯さないでおくよ。」と言うのだった。大学時代からのつきあい。お互いをよくよく知っている。束縛しないのだ。私は地元に帰り、彼は元々東京で、今は一人暮らしをしている。
「彼氏いるんですか」
圭一が聞いてきた。
「いますよ。」
そして続けた。
「私は飲みたいから来てるだけ。男をさがしているのではないの。」
「そんなこと思ってないですよ。」
「ホント? 良かった」
経験上、よく聞かれた。お店の人が私を理解してくれれば、それで良かった。
「そうよ。友美ちゃん、ノリはいいけど、ガードは固いのよねえ」
「そうです。酔っ払うことと、男と女の話は私的には別分野。」
そのあたり彼も十分わかっていて、ふたりの仲は続いている。
「トモミさんというの? 僕は二条圭一です。出張で時々来てます。どうぞよろしく。」
「ごていねいにありがとうございます。私は有川友美です。」
「じゃあ皆で乾杯しましょうか」
ママがグラスを持ってきた。
「乾杯」
そうして圭一とは飲み仲間になった。
当時ケータイは今ほどではなかった。私は持っていなかった。別に不便を感じた事もなかった。なのでアドレス交換もない。『u』に来てたまたま逢えば、一緒に飲むという感じだった。
知り合って、いろいろな話はした。北海道札幌の話はとても興味があった。数回旅行したし、同じ北国といっても、札幌は大都会で雪国の質が全く違う。
「来てくれたら案内するよ。と言っても僕も正月しか帰ってないんだ。雪まつりなんて十年近く見てないよ。」
「私は一度だけ見たわ。」
「こんなふうな雪像がいっぱいあったろう?」
と、メモ帳にスラスラ描き始めた。
「圭一さん、絵が上手。好きなの?」
「うん、よくスケッチするんだ。」
「もしかして、いつも持ち歩いてたりするの? だって圭一さんのカバン大きいでしょ?」
「ああ、これは違うよ。仕事で使うものが沢山あってね。」
まだアナログの時代だったのだ。
「スケッチブックは小さいよ。」
カバンから薄い一冊を取り出した。
「それ見たい。」
「いや、これはダメ。ただ趣味でテーマなく書いているだけなんだ。」
「へぇ」
「これは山形ノートなんだ。土地別に分けているんだ。厚いやつだとかさばっちゃうだろ。出張前に選んでくる。」
「これは新しい発見。圭一さんってマメなとこあるのね。」
「そういうわけじゃないけど、そういう事が楽しいんだ。」
「んー、山形編と聞いて、ますます見たくなった」
「ダメダメ。がっかりするだけだよ。」
「やっぱり見たい。ねぇ、ママもそう思うよね。」
「嫌がる事はやめなさい。飲みものをこぼしたりしたら大変だし。」
「えー、見たいなぁ。」
圭一はそれをカバンにもどした。
「今度、いい出来、と思ったら、見てもらうよ。」
「必ずですよ。約束ですからね。」
私は圭一と顔を合わせる度に、そのことを思ったが、あまりしつこくするのも失礼だと、言わないでいた。そして段々忘れていった。
圭一が私の勤務先に電話をくれたのは、それから一年以上経過した二月だった。
「会社に電話してごめん。自宅の番号メモをなくしてしまって。」
「びっくりしました。どうかしたのですか」
「何か口調が違うね、仕事中申しわけない。」
「一応仕事してますので。笑わせないで下さいね。」
「今日、花小路いく?」
「残業するかもしれないので、まだわかりません。」
「得意の予定は未定、かな」
「そう、ですね。何かありましたか?」
「うん。ちょっとね、来月の転勤が決まったんだ。」
「え?」
「高松の支店に行くことになったんだ。東北出張はなくなるかな。」
「圭一さん、今どこにいるの?」
「東京」
「だってさっきuに行くかって」
「明日は土曜だし、つばさに乗って自費出張。」
「わざわざ?」
「わざわざ。転勤の話を聞いたら、急に。」
「何時に着くの?」
「九時前には」
「わかりました。私も行きます。」
「ありがとう。あのさ、友美ちゃん、デートしよう。」
「は? おかしいわ、あらたまって」
「花小路に行く前にさ。」
こんなことを言われたのは初めての事だった。圭一の転勤よりも、「デートしよう」の言葉にドキドキした。いつも隣の席で飲んでさわいでいるのに、どうしたものか。
(私、今日、どんな服着てきたっけ?)急にソワソワしはじめる自分がいた。
待ち合わせは駅前の居酒屋にした。あえてそうした。おしゃれな店にしたら、まるで本当のデートになってしまいそうで、こわかった。
「やっぱこれでしょ。生二つ」
いつものノリで二人は食事をした。圭一は「山形に来ることもなく、花小路に行くこともなくなるのか」と、さみしがった。
「遊びに来ればいいじゃない」
「そうだけど。遠くなるなぁ」
朝から降った雪がようやく止んだ。
「ママに電話しておいたわ。驚いてた。」
「全く残念だよ」
私がタクシー乗り場に行こうとすると、圭一が、「歩いていかない?」と提案してきた。
二人は歩き出した。日中も解けなかったので、踏みしめる様な雪だった。
「昼間に天気がいいと、雪が解けるでしょう。それが夜に凍って朝はつるつるになるの。山形弁ではそれをテカテカって言うのよ。」
「また降ってきたよ。」
「私かさ持ってきた。使う?」
「まっ赤だ」
とりとめない話をしながら、ゆっくり歩いた。
「あのね」「?」
「あのさ」「?」
お互い息をのむ。そのあと続かない。
「歩くと遠いわ」
「もう少し。冷たいビールが待ってるよ。」
多分、ふたりは同じ事を思ったはずだ。
「家に来る?」「部屋に来る?」と。
でもどちらも言えなかった。あの場面ならどちらも断るわけがない。でも、二人とも言えなかったのである。
「今日は同伴ですよ。」
「あら。遅かったのね。」
「駅前から歩いてきたの。店に着く少し前におもいっきり転んだ。傘がむこうまで飛んで行っちゃった」
「圭一君の第一回、送別会だわ。飲もう。」
いつも通り楽しい時間だった。
圭一と逢ったのはそれが最後になった。
そして五年が経ったのだ。
あの時約束したスケッチブックを手にしてみる。きれいな線で描かれている。山形駅、上山駅の外観、山寺駅もあった。どこかの公園、文翔館、新幹線つばさの絵、十五枚あった。最後の一枚は、『u』へ行く小路だった。
胸がしめつけられた。
あの雪の日だ。小さく赤い傘が宙を舞っている絵――。
「友美ちゃん、テカテカだよ。」
「ホント。スケートできそうね。」
調子に乗って滑って歩く。子供みたいな気持ちで楽しかった。その時、どこかの店の扉が開き、内
の音楽が流れてきた。
「これラストソング。私好きなんだ。」
「いいねぇ。僕も好きだな、この曲。」
「ラララララララ・ラ・ララ」
合わせて滑った。小雪も合わせて舞っていた。
そして、つまづいて転んだ。傘が飛んだ。
圭一の絵には、赤がそこだけ塗られていた。
私と圭一さんだけの思い出だった。
(圭一さんが死んだなんて……)顔を合わせることがなかった分、よけいピンとこない感じがする。
私はスケッチ本を持って出かけた。
「圭一さん、私もここを離れるの。これ大切にします。」
日が暮れかかってきた。
(今夜は一人偲ぶ会ね。)
スケッチにつぶやいた。