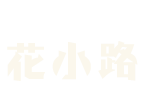物心ついた頃には「頭のいい子」ということになっていたけれど、当人にしてみれば、わからないことをわからないままにしておくことのほうがすっきりせず辛いのだ。時間
帯や曜日に関係なく出勤する両親は、ごく自然に、自分が読んだ物をわたしに与えた。新聞、雑誌、ハードカバーでも何でも。わたしはいつも、それらの文字を片っ端から
追っていた。スポーツカーを運転したことはないが、そのハンドルを握って、時速二百キロ超でぶっ飛ばしているような感覚だった。読み物達とわたしの時間は潤沢に流れ、高校は、やはりあそこに入った。あそことは、そう、そこだ。
高校というところは、必ずしも行かなければならない場所ではない。そもそも人が、必ず行かなければならない場所などない。何処かへ行くのは、その人がそこに行きたいという願い、我が儘だ。「行かされる」というのも、やんごとなき事情への了承という、「行きたい」の消極形ではないかと思う。
さて、高校生活がスタートしてみると、どうも気持ちとカラダが噛み合って回っていない感覚がある。すぐにチェーンがからんでしまう自転車のようだ。校内で同類の自転車に出会わぬのなら、不具合の原因は学校側ではなく、こちらの側にあるのだろう。「行きたい」の不在。あっさりと示せたが、では行きたくなりましょう、ハイ行きたく
なりました、とはいかないものだから、そのまま、わたしの日常は連綿と続く。
その日は、学校の帰りに書店に立ち寄ろうと校門を出たものの、歩いているうちに、買うためでも探すためでもなく、ただ何となく書店に向かう自分のことを、不思議な程、どうにも許せなくなってしまった。鼻腔がつうんとして、歩みは止まり、涙と鼻水が同時に一滴ずつ落ちた。思わず公道にこぼしてしまう程、みっともなく、何をそんなに抱えているというのだろう。スクールバックからポケットティッシュを取り出し、二度、鼻をかんだ。
左に、花小路と書かれたアーチがあった。日中だから、電飾はまだ灯っていない。人通りもない。呼ばれていないから逆においでおいで。わたしは、左へ折れ、アーチをくぐった。
音が聞こえる。水道の蛇口をひねる音、ガラスや瀬戸物の食器が、カチャカチャと重なりあう音、ジャージャーと油で炒め物をする音。「やんだぁ」という中高年女性の喋り声。イントネーションから察するに、これは、雨が「止んだ」のほうではなく、標準語訳「いやだわぁウフフ」のほうに違いない。
気配だけを感じる。リズミカルで、磊落で、清潔な気配。
弛緩。尖った形をしていた何かが、ゆっくりとわたしの中で、線形を変える。
この日以降、わたしは何度、学校の帰りに花小路のアーチをくぐったことだろう。今となっては、ちゃんと数えておけば良かったと思ったり、その正確な数を知ったら衝撃を受けそうで、やっぱり数えないで良かったと思ったり、揺れる振り子だ。
放課後、教室の机で、瞼を閉じ加減にしたわたしは、ただ入り込んでくる音を受けていた。ブラスバンド部のパート練習、ホイッスルと、ラスト一周、の掛け声。皆、偉いねえと、心底わたしは感心した。毎日、高校生らしく、周囲を安心させることができているのは、本当に偉いと思う。
できるよ、同じようにしてごらん、なんて言われたら、わたしは余計できなくなりそうだ。じっと待つ。わたしの必然性を。
社会の時計は、見てるけど、合わせなくては、とは思わない。まだ待ってるものが来ないんだもの。
今日もこうしてまた少し、皆とズレただろう。けれども納得できるのは、どうしてなんだろう。
立ち上がって教室を出る。花小路へと向かう。
三者面談は、わたしの進路がテーマなのに、人ごとみたいな距離感があった。発言を促され、ついにわたしは、入学して以来ずっと、通学の意欲がないまま今日に至っている、と述べた。現在、何か困っていることは?と尋ねられたので、困っていませんと答えた。次に大丈夫か?と問われたので、「大丈夫です。」と返した。担任教師は安堵し
たように、「今日来たみたいに明日も学校に来て、そうしていれば、気持ちはついてくるから」と言った。
反射的にわたしは「すみません、明日は学校へは来られないかもしれません」と返答していた。「何か、おかしな話をしたかな」「いえ、そんなことはないと思います」「じゃあ、なぜ急に、お母さんや先生が驚くような事を言うのか、説明してくれないか?」
わたしは三秒程の間をもらい、話し始めた。無理みたいです。気持ちがついてこないまま行動することは。気持ちを器用に扱えないと自覚しつつも、わたしは精一杯、誠実に、気持ちに寄り添います。それがわたしにできる、ささやかで、唯一の、幸福な態度です。かけがえのない羅針盤、それが気持ちなんです。その羅針盤がぴくりとも動いて
いないんですから、行けないんです、やっぱり。「だから、通学しているうちに、気持ちが動き出すんだよ。大学を目指してるんじゃないか」と、担任教師はなおも、わたしのために言葉を重ねてくれたのだが、わたしが、「先生、そういう方もいらっしゃるだろうと、わたしも思っています。そして同時に、そうではない方もおいでかと考えます。なぜなら、どうやらわたしが、そちらに属する人間のようだからです」と返すわ、隣に座っていた母は、二つ折りの携帯電話を折りたたんだみたいな形でうなだれてしまうわで、すっかり紛糾状態となってしまった。
わたしは、まだまだだなと感じた。先生と母に、もっとスマートに、穏やかに、話を持っていくことができたのではなかろうか。
先生、お母さん。わたしはどうやら、わたしを丸ごと認めているようです。
わたしは生徒だから、先生は、無意識に、さすがは先生、とか、先生ありがとうございます、というリアクションを期待なさっておられることでしょう。けれども先生は、ひとりの人間として、もともとわたしへの責任がありません。わたしの責任をとれるのは、わたしだけなんです。言葉は常に、発信者に向かって放たれています。だから、良
いのです。だから、しっかり聞かないといけないのです。そうですよね先生。
お母さん、どうか安心して下さい。だってそんな変な姿勢のままで、ずっといられないでしょう? 散々な気持ちも、永遠だったことなどないでしょう? もちろん、時間が必要かもしれない。けれど、お母さんなら、絶対大丈夫。今日はわたしのために、中学校の三者面談以来、有給休暇を取ってくれて、どうもありがとう。
やっぱり花小路の方へ足が向いてしまう。雨粒がぽつ、ぽつと降りたかと思っていると、一気にザアッとやってきて、咄嗟に一軒の軒先に飛び込む。カバンからタオルハンカチを取り出して、濡れた髪をそっと押さえる。
「お姉ちゃん、お姉ちゃん」と呼ぶおばちゃんの声がする。「お姉ちゃん、高校生かい? 高校生じゃなかったら中に入ってもらってもいいんだけど、高校生だったら、出入りしているとこ知ってる人に見られて、面倒な話にならないとは言えないからねぇ」
どきりと心臓が鳴る。わたしに話しかけているのだ。これだけ花小路を訪れていながら、誰とも顔を合わせたことがなかったのは、そういうことだったのか。
「お姉ちゃんは、神様だからね」
カミサマ? そう聞こえたが、聞き違いだろうか。
「お姉ちゃんが、ここ、通るようになってから、びっくりだよ。それまでずうっと来てくれてて、突然すぱっと来なくなったお客さんが、十数年ぶりにふらっと入口のところに立っててさ、あれは、うっれしかったねぇ」え?
「そう、お客さんね、毎年毎年、年取っていくでしょう? だとね、当然いつかは来られなくなる、ウン。だからね、新しいお客さんが来てくれるようにならないと、店は続けていけないんだよね。毎年、ジリッ、ジリッと、実は売り上げ、下がってた。体力も気力も落ちてくるし、弱気になってきてたかなぁ、お姉ちゃんが通るようになるまで
は」 何? 何が起きた?
「女性のお客さんね、二十代、三十代、四十代くらいの若い人達がね、来てくれるようになったのよ、来たよーおばちゃんって。コラーゲン? ポ、ポリ、ポリフェノール?化粧品より、食べ物を楽しく頂くのが美容に効くとかで、ホント、今の人達はよく勉強してるわ。お姉ちゃんも、学校、頑張って。お姉ちゃん、制服ないんでしょ? 優秀な
んでしょ?」いえいえ、立派な問題児ですと、説明したいが難しい。
「まだ高校生なんだから、甘えていいんだよ。疲れたら、休んでさ。そうして、思いっきり好きに生きたらいい。親御さんも、きっとそう思ってるよ」
何、言ってるの、おばちゃん。
雨はとうに止んでいる。
大学進学に関してはひとまず脇に置いておくことで了解を得、高校も休学手続きをとった。すっきりとしたら、不意に、旅に出たくなった。具体的にはサンフランシスコとメキシコ。空が見たい。歩きたい。空の青。そして土。
どちらか一方では駄目かと父が言い、父の卓上地球儀を持ってきて、一回で同方面の二箇所を訪問する方が、別々に二回訪れるよりも効率が良いと説明した。晴れてわたしはサンフランシスコとメキシコへ旅立った。
お金をだいぶ使わせてしまったが、旅行は、大正解だった。これから行かれる方もおられるかもしれない。親愛を込めて、ここでは詳細についての記述を略す。
友達もできた。なんと男の子。サンフランシスコに向かう機内で、気分が悪くなっていたわたしに、「窓から、いい景色が見えますよ、替わりますか」と、話しかけてくれたのがきっかけだった。ここは助け合いの場面だ、と彼は思ったそうだ。お互い、ひとりで踏ん張っている自覚がある。だから友達になれた。連絡は、とり合わなくても平気
だ。
好きにやらせてもらってみたら、それに見合う何かを返したいと思うようになった。わたしは、復学してもいいかな、それもおもしろいかなと思えてきて、次の新学期からまた、学校に通い出した。年下のクラスメイトが、語学留学してきた先輩が戻ったと誤解するのを、微笑でかわした。
花小路を歩くことはなくなった。あの雨宿りの日から、一度も。
おばちゃんは、嘘を語ってはいなかっただろう。わたしが花小路に通うようになって、不思議な事が起こったと本気で信じられるのなら、それがおばちゃんにとっての真実だ。
そしてわたしは、おばちゃんに起こった出来事とわたしとは、関係がないと思っている。ずっと顔を出さなかったお客さんがまたやって来たのは、おばちゃんがおばちゃんだから。新しい女性のお客さんが来るようになったのも、おばちゃんの才覚。わたしが、神様であるわけがない。もし神がいるのなら、それは、その人自身だ。
美味しいお酒をこよなく愛する教授とは、やはり旅が御縁だった。「大学は? そう、じゃあウチに来て、手伝ってよ」と言われ、卒業するまで待っていて下さいと答えた。
教授は、きれいな大人だ。昔も、きっとこの先も。「この報告書まとめたら、行っちゃおう、山形。オイシイんでしょ?」「そんな時間、あるんですか」「時間は、つくるの。新幹線で行って帰ってくるくらい、出来なきゃ。人として」人として、ですか。
「山形はね、行きたいところがあるの」「そうなんですね。どちらです?」「花小路」
その一言が、一瞬、わたしのすべての動きを止めた。
教授は、アーチがうまく撮れないや、と、何度もシャッターを切っている。夜の花小路は、まるで知らない光景みたいだ。
「よし、ここに入ろう」と教授が選んだのは、あのおばちゃんの店だった。ガラガラと引き戸を開けると、「ハイいらっしゃい!」と元気良いお出迎え。ああ、この声。
教授は終始ご満悦で、「いいのいいの、自分で注ぐから」と、旨そうに飲み、食む。
「お客さん、そう、東京から。わざわざ遠くから、ようこそおいで下さいました。あのね、これもちょっとつまんでみて。結構そのお酒と合うと思うから」と、おばちゃんは、絶妙の間合いで次、またその次と、教授に器を差し出す。わたしは、よく出汁のでたスープをちびちび頂きつつ、二人を見守っていた。既に二十歳を過ぎており、お相伴
に与り一応お酒の方にも口をつける。だが、今夜は飲んだ気がしない。致し方ないだろう。
結局、何も話さずお店を後にした。もう、おばちゃんの中に、わたしは棲んでいない。ちっちゃなあの日はとっくの昔に終わってる。わたしも、終わりにしていい、はずだ。
その日のうちにお店のテーブル、雑巾で全部拭くところまでやってしまわないと、どうにも落ち着かないのよ。お客さんの座る場所でしょう。
そうやって毎日毎日、同じようにちゃんとやってると、いざ、っていう時も、慌てないの。だって後悔したくないもの。わかってたんだね。あたしの神様は、また来るって。
今日、年上の女の人連れてお店に入ってきた時、一発でわかったさぁ。すっかり、いい娘さんになってた。話なんて、いいよ。そんな、あたし、神様となんて。英語だってしゃべれないし。