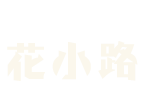アーチ通りを左折して、さらに中通りの路地を左折すると袋小路に突き当たる。澤邊清松が《花小路》のアーチでタクシーを降りたのは十分前のことだ。たかだか徒歩一分程の距離だが、米寿も近い清松にはそれでもかなりの道のりだ。いや、七十年振りともなれば、むしろ瞬きのような時間なのかもしれない。
清松はパナマ帽を脱ぎ、袋小路の先を見上げた。こんなにも小さな街であったか。十七歳の頃の記憶が問いかけてくる。専称寺の蝉の声は、いつしか鳴き止んでいた。
『蛍月』の古びたネオン看板が、変わらずにそこにあった。驚きと感動が、杖の歩行には不向きな狭い階段を急がせた。清松は重厚な扉の前で立ち止まった。あの時、不安と後悔から何度も引き返そうとして迷い込んだのがこの扉だった。志願兵に出征のためらいなどあるはずもなかった。だが入隊の日が近づくにつれて、言いようのない焦燥感が
込み上げてくるのだった。
あの日、あれ程重く感じた扉は、カランと軽快な音を立てて、清松を招き入れた。
「いらっしゃい」
澄んだ若い女の声が、七席のカウンターだけの室内に響いた。あの時と同じ内装だったのかは定かではない。女は藍染の浴衣を着ていた。柄は満月に蛍。刹那、あの時の記憶が鮮明に蘇り、清松は茫然と女を見つめた。
「夢クラブさんなら、この先ですよ」
女は清松の視線を断つように声を掛けた。
「あ、いえ、私はここに……」清松は我に返ったように狭い店内を見渡した。
「あら、御免なさい。てっきりシニア婚活のお客さんかと思いました。最近花小路に来て下さるご新規さんは、婚活カフェ『夢クラブ』さんのお客様がほとんどですから」
女は清松のパナマ帽と杖を受け取ると、無人のカウンターの一番奥の席に誘った。
桑畑だったこの一帯が、市内有数の歓楽街として発展したのは、明治の大火で料亭「千歳館」が移転して来てからと聞いている。花街という響きは、少年の頃の清松にとっては夢の世界であり、大人への憧憬をかき立てた。今でも昭和レトロの雰囲気を漂わせてはいるが、若者を呼ぶには刺激に欠け、観光化するには土着性が濃過ぎる。賑わ
い振興にと、シニア向けの婚活に街ぐるみで取り組んでいることは新聞でも紹介され、清松も知っていた。
「こんな死に損ないの老人が、婚活に見えますかな」清松は、精一杯明るく笑おうとしたが、声が擦れて笑い声にならなかった。
「尚美です」女はおしぼりを手渡しながら、ちらっと清松の手首辺りを見たようだが、
すぐに飲み物を訊ねた。
「私は、お茶で。あ、いや、これは無粋だったな。お茶では商売になりませんな。ではビールをいただけますか」
「お茶でも結構ですよ」
尚美は笑顔で応え、カクテルでも置くように、丁寧に冷えた麦茶をカウンターに乗せた。
尚美は黙ってお通しの冷奴を作り始めた。一見の客にあれこれ訊こうとせずに迎え入れてくれるのも、あの時と同じだった。
「旭座は解体したのですね。タクシーから見て驚きました。専称寺が見通せて、あんなに近かったのですね……」
清松は沈黙を気遣い、口を開いた。
「シネマ通りの象徴だっただけに残念ですわ。映画の帰りに寄ってくださる常連さんと映画の話をする楽しみもなくなりました」
「私もあそこでよく映画を見ました。まだ売り子さんがいてね。煙草の煙が蔓延する中で冷凍みかんやキャラメルを食べながら、ジョンフォード監督の駅馬車やチャップリンの黄金狂時代などを観ましたね。何と言っても圧巻なのは風と共に去りぬでしたね。スカーレット役のビビアンリーが実に綺麗で、クラークゲーブルに本気で嫉妬したくらい
ですよ」
清松の弱々しい口調は相変わらずだが、いつになく心が沸き立つのを覚えた。その威を借りて、思い切って訊ねてみた。
「実は、このお店に来たのは二度目です。もう七十年も前になりますが。失礼だが、あなたは、月代さんという女性をご存知ではありませんか? 源氏名だったかも知れませんが」
尚美は驚いた様子で冷奴を出す手を止めた。
「祖母を、ご存じなのですか?」
「それでは、あなたは月代さんのお孫さんですか! 月代さんも同じような浴衣を着ていたもので、もしやとは思ったのですが」
「これは祖母の形見です。夏は雰囲気作りもあり、浴衣で出るようにしているのです。特別な日は……これを選ぶのです」
清松は、愛しむように浴衣を見つめた。
月代さんは十五年前に他界していた。倒れる前日までお店に立っていたという。
あの日は、清松の予科練合格を祝い、親戚一同が千歳館で祝宴を開いてくれていた。
八人兄弟姉妹の貧しい百姓家には、千歳館など場違いだと、母は頑なに辞退したが、遠縁筋の助役の勧めもあり、冥途の土産とばかりに田舎者の狂宴が行われたのだ。いつしか酔った助役の長い演説が始まっていた。
「兄二人は既に出征し、五男坊の清松は自ら志願し、予科練合格を果たした。なれば澤邉家は愛国の鑑であり、ワシもお国に対し鼻が高い。そもそも報国とは……」
主役清松の存在も薄らいだ頃、清松の好奇心は、憧れだった隣の花小路へと移っていた。そして、厠への道は小さな冒険となったのだ。
「尚美さん。やはりお酒を戴けませんか。月代さんを、少し偲びたくなりました。大分遅くなってしまいましたが……」
「有難うございます。祖母も喜びます。何を差し上げますか?」
「ニッカは、ありますか?」
「勿論です。祖母の代からこの店の十八番ですから。”竹鶴”で宜しいですか?」
清松は、にこっと、静かに頷いた。
薄暗いネオンに照らされた路地のアジサイに蛍が灯っていた。興味本位で迷い込んだ世界は、童貞の十七歳にはあまりにも華やかだった。不安と後悔を、故郷の見納めとばかりに打ち消して、袋小路の鈍詰まりにあった『蛍月』という店で覚悟を決めたのだった。
「坊主、筆おろしは済んだのか」とからかう客を叱りつけ、客が月代ママと呼ぶ浴衣姿の女は、十七の少年に戸惑うこともなく優しく迎え入れてくれた。筆おろしの意味も分からない少年は、ただ西部劇で観たジョンウェインのように、酒場という空間に身を置くことで、大人になれる気がした。言いようのない不安を消し去る強さが欲しかった。
「ご卒業か何かのお祝いですか?」
清松の胸ポケットから祝儀袋が覗いている。清松は、隠すように慌てて押し込んだ。
「あ、はい。来週、予科練に入隊します」
「まあ、それはおめでとうございます。優秀なのですね」
「いえ、ただ、今はお国のために一日も早く前線に出て、撃墜王の坂井三郎飛行兵曹長のような立派な飛行機乗りになりたいと思います!」
「頼もしいこと。でも、怖くないの? 逆に撃墜されることもあるのでしょ?」
「怖くなんかありません! もし、そうなったとしても、お国のために死ねれば本望です」
「でも……お母さんは悲しむでしょうね」
月代さんの目が、少し悲しく見えた。
「いえ! きっと喜んでくれます!」
清松は、千歳館の高級料理にも手を付けず、無言で座っていた母の顔を思い出していた。
「ではお祝いにサイダーでも召し上がる?」
「いえ、お、お酒を下さい!」
月代さんは少し驚いたようだったが、直ぐに笑顔を返してくれた。清松の前に置かれたのは、美しい琥珀色のお酒だった。
「大日本果実社のウヰスキーよ。今は日果と呼んでいるわ。海軍さんが独り占めしているので今は統制品だけど、今日は特別」
周りの客が羨望の目を向けている。
「あなたお名前は?」
「澤邉清松です!」
「松に竹鶴か、縁起がいいわね。竹鶴というのはね、このお酒を造った人の名前よ」
清松はウヰスキーを一気に流し込んだ。焼けるような強烈な刺激が喉を襲った。嗚咽で呼吸も儘ならない。客の嘲笑が耳に聞こえる。月代さんは直ぐに水を差し出してくれた。
「そんなに無理して大人ぶらなくていいのよ」月代さんはカウンターを拭きながら、話を継いだ。
「ウヰスキーの色はね、何年も何十年も掛けて樽から染み出した色なのよ。時間を掛ければ掛けるほど優しくまろやかになるの。そして、嬉しい時も悲しい時も、淋しい時も、飲む人の心を癒してくれる、それがお酒の役目。物でも何でも、生まれたからには必ず全てのものに役目があるの。人間も同じ。年を重ねるほど優しくなれる。生まれたからには、その人が果たさなければいけない役目がきっとある。清松さんにも、必ず」
「だから僕は、お国のために」
「バカを言わないで!」
突然、月代さんの大声が響き渡った。客が一斉に振り返った。その迫力に、清松はすくみ上がった。月代さんの目が潤んでいた。
「人の役目はね、生きて、生きて、どんなに苦しくても必死に生きて、それで初めて果たせるの! 中途半端に熟成したお酒で誰が喜びます! そんなので人を幸せに出来ますか! お国を守ることは、死ぬことではありませんよ! 生きて人の役に立つこと、それが、国民を幸せにすることです!」
店に沈黙が流れた。月代さんの言葉は新鮮であり衝撃だった。同時にそれは、禁句でもあった。玉砕が美化される時代であった。少なくても、戦場に向かう若者へ送る言葉ではなかった。
憲兵も恐れない月代さんの凛とした姿に、清松は無性に体が震えるのを感じた。言いようのない焦りや不安の正体が今、胸を突き破って体現した。死に対する、恐怖。さらに自分の臆病さを自覚した瞬間だった。十七歳の心は、まさに破裂しそうであった。
「清松さん。死に急いではいけませんよ。死ぬのは誰でも怖いものです。自分に正直になりなさい」
諭すような月代さんの言葉に、いつしか清松は十七の少年の心に押し戻されていた。
涙が無性に流れた。月代さんはお粥を作ってくれた。それを食べながら、また人目も気にせずに幼子のように泣き続けた。
食べ終わると月代さんは、店の神棚から何かを持て来て清松の手に握らせた。穴の開いた五銭玉だった。
「五銭は四銭、つまり死に際の死線を超えるから、必ず無事に帰ってこられるわ」
清松は五銭玉を握りしめ無言でお店を出た。
「死ぬ時は、必ずここに戻って来てからにしなさいね」月代さんは扉まで見送り、清松の背中に声を掛けた。月代さんの浴衣の満月に、一匹の蛍が停まって仄かに光った。
「清松さん。お迎えですよ」
清松は久しぶりの竹鶴に酔いしれ、転寝をしてしまったらしい。尚美に起こされると、一人の男の顔がおぼろげに映った。
「お父さん! いや会長、黙って居なくなるなんて、どういうつもりですか!」
「雅夫か……どうしてここが」清松はかすむ目を擦った。
「今は携帯にGPS機能があるのです! でも、お店までは判りませんから、随分探しましたよ! 変な気を起こされたらと、まったくいい加減にして下さい!」
雅夫は一通り文句を言って気が済んだのか、疲れ切った様子でカウンター席に座り込んだ。
「息子さんですか?」尚美は冷たい麦茶を差し出した。雅夫は一気に飲み干すと、清松の掛けたであろう迷惑を詫びた。
「今日、清松さんが祖母を訪ねて来て下さるなんて、とても不思議で。実は、今日は祖母の命日なのです。もし宜しかったら、祖母直伝のお粥を召し上がって戴けませんか?」
清松が転寝している間に用意したのであろう、楚々としたお粥が二人の前に並んだ。
「麦を梅干と昆布だしで煮込んだだけのお粥なのですが、気持ちが落ち着く魔法のお粥だと、生前よく祖母が言っていました」
清松はゆっくりと口に運んだ。
「あ、あの時の、味です……」
瞼にある出来事が蘇った。鹿屋飛行場を飛び立って三十分。清松のゼロ戦から白煙が上った。清松は五銭の入った御守を握り締めた。
『清松、帰還せよ! 機体の故障は運命だ! 無駄死にするな! 命令だ! お前が言っていた店で、お粥を肴にニッカを飲みたかったな。咲くもよし散るも又よし山桜。さらばだ!』
隊長の無線の声が、今も耳から離れない。
「労わって上げて下さいね」尚美が雅夫にささやいた。雅夫が怪訝な顔をした。
「清松さんの手首に大きな点滴瘤があったので。実は私、以前看護師をしていました」
「そうでしたか。あ、申し遅れました」
雅夫が名刺を差し出した。
「東京の大田区でガラス工場を経営しています。戦後父が裸一貫で創業しました。本物のウヰスキーを飲むには本物のグラスでなくては失礼だとか言って、一からガラスを勉強したそうです。三十人ほどの小さな会社ですが、今は迎賓館の晩餐会にも使って戴けるようになりました。会長に退き、暫く東京で入院していました。しかし本人の希望で
故郷の病院に転院することになり、昨日山形に来たのですが、今日ホテルを抜け出してしまって」
「そろそろおいとましようか」清松は、雅夫の身の上話を遮るように立ち上がった。そして、ポケットから何かを取り出した。
「これを月代さんにお返して戴けませんか。自分の役目を果たせたのかどうか。でも、何とか、ここに来る約束は、果たせました」
清松は五銭玉を尚美の掌に載せた。
「これは!」
月代さんには芸妓時代があった。民政党員のお妾として男子を産んだが若くして戦死。
直ぐに離縁され店を始めた。その後結婚したが、その子に五銭を渡せなかったことを一生悔いていたと尚美は話してくれた。改めて月代さんの五銭に込めた思いを知り、清松は涙で敬礼を続けた。『死ぬ時は、必ずここに戻って来てから』月代さんの声が聞こえたような気がした。清松は安らかな顔で店を出た。
転院は緩和病棟であろう。元看護師の尚美には分かっていた。独りで祖母の命日を閉店日と決めていた。最後のお客様を見送り、尚美は神棚に五銭玉を祀り静かに手を合わせた。明日からは母の介護に専念します……。清松のグラスの氷が、カランと店に木霊した。